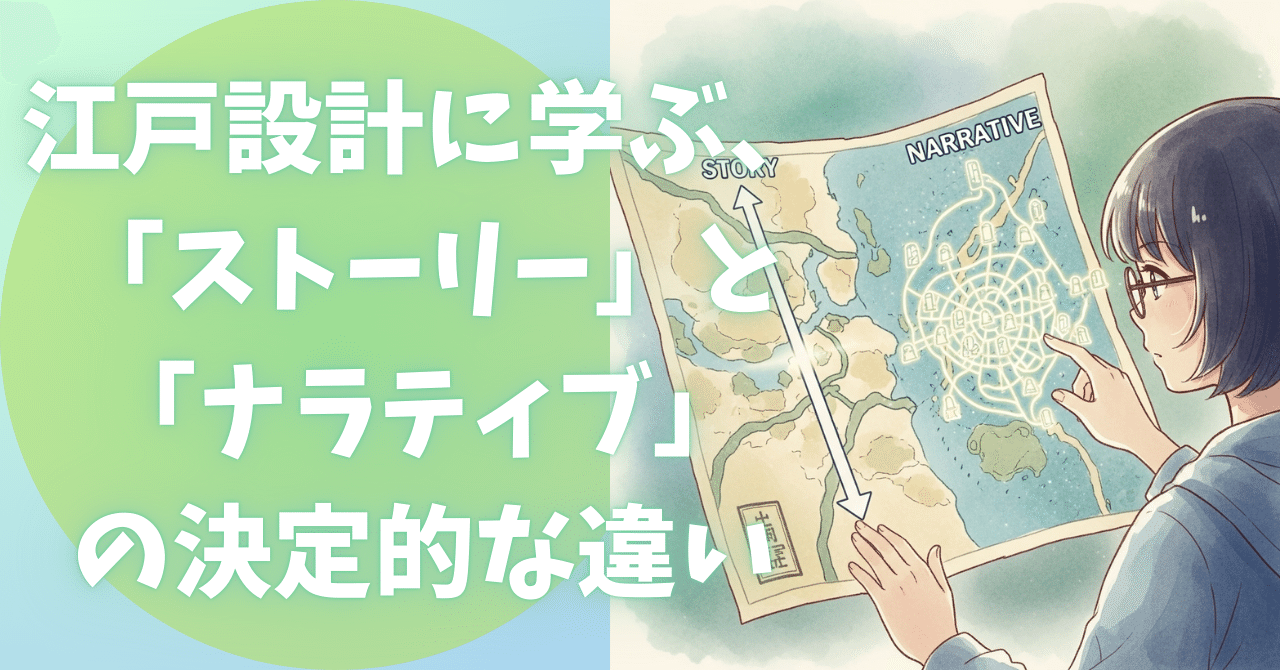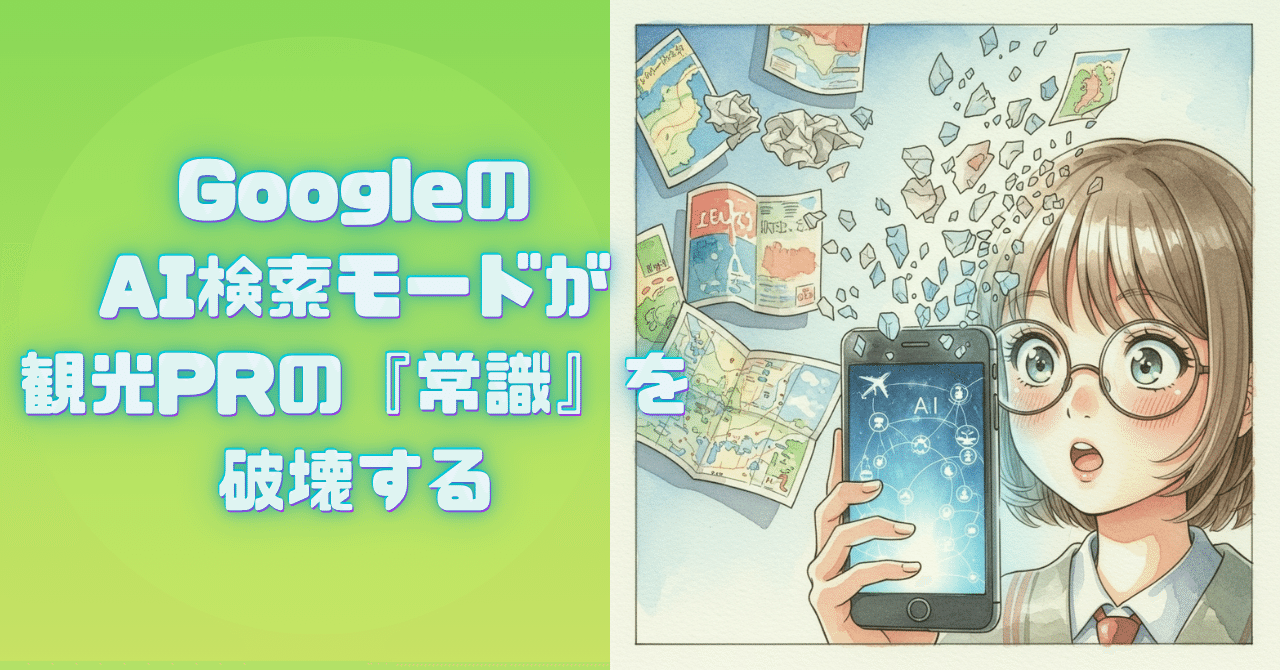「おしい」観光ストーリーを、
「価値ある」体験に変える方法
「文化観光のストーリー化」。
近年、あらゆる地域の計画書で目にする、魔法の言葉です。
しかし、その言葉の本質を、私たちは本当に理解できているでしょうか。
地域の歴史を年表のように並べることや、ただ案内マップを作ることが「ストーリー化」ではありません。
本当の物語化とは、点在する資産の背景にある「なぜ」を掘り起こし、訪れる人の心と地域を強く結びつける「体験」を設計すること。そして、見過ごされてきた「その話」に、誰もが納得する「価値」を与える知的なプロセスに他なりません。
このページは、長野県上田市柳町と石川県加賀市大聖寺を舞台に、私たちがその「価値の翻訳」をどう実践しているのかを解き明かす、一つの具体的な事例報告です。
上田城下町文化観光ストーリー誕生までの解説
人の心を動かす「物語」には、いくつかの必須要素があります。
それは、読者が感情を投影できる「登場人物」、その人物が直面する「葛藤や変化」、そして共感を呼ぶ「テーマ」です。
このうちどれか一つが欠けても、物語は成立しません。
この原則を元に私たちが上田市の現地調査で発見したのは、他地域と比較しても際立っている、人々の「食」への意識の高さでした。
例えば、包丁と食材への感謝を捧げる「四条公神社」や、今なお続く正月の「七草儀式」といった文化資本。
そしてもう一つ、城下町のあちこちに点在する稲荷社の祭神名に、「宇迦御魂神」と「倉稲魂命」という二つの異なる表記が混在しているという、重要な事実です。
この、一見些細な表記の違いにこそ、上田の持つ二面性、すなわち「秩序」と「創造」の葛藤が秘められているのではないか。
私たちはその着想を物語の専門家へと伝え、以下の寓話が創作されたのです。(※北国街道の話は後述)
この寓話は、昔話のスタイルをとる4部構成の物語であり、それぞれが独立して成立するよう設計されています。「クラモリ様」と「ウカノケ様」という二柱の稲荷神は、上田城下町の文化が持つ二面性を象徴しています。
このストーリーをベースにすれば、「四条公神社」や「美味だれ焼き鳥」といった現代の食までを一つの文脈で繋ぐプロモーションが可能となり、文化と現実がシームレスに結びつきます。
そして、この構想はすでに次の段階へ進んでいます。寓話で描かれた神々の話をベースに、舞台を北国街道へ広げた現代小説を専門家に依頼し、制作しました。
核となる物語があることで、このような二次的な創作展開が非常に容易になるのです。
こうして派生作品を増やし、別の角度から描かれた物語同士が新たなキーワードで結びつく時、そこに「物語の接点(ノード)」が生まれます。最終的には、地域文化全体を網羅する、網の目のようなストーリー構造を構築することが我々の目標です。
それは、中心からではなく、各要素が相互に繋がりながら広がっていく「曼荼羅」のイメージに近いかもしれません。ストーリー化とは、一話作って終わりではないのです。最初の一歩はありますが、最終的に出来上がる世界には、絶対的な中心は存在しない。それがこの取り組みの最大の特徴です。

なぜ、多くの「ストーリー化」は“物語”になっていないのか?
「ストーリー」と「情報の羅列」の混同
地域の歴史や文化財のスペックを時系列で並べただけでは、人の心は動きません。
それは単なる「情報」であり「物語」ではないからです。
もし『クラモリ様とウカノケ様』の話がなければ、上田城下町柳町は、「真田氏ゆかりの城下町」「歴史ある北国街道の宿場町柳町」「信州名物の味噌と味噌ラーメン」などという情報の羅列で終わっていました。
しかし、「厳格なクラモリさま(秩序)」と「陽気なウカノケさま(創造)」というキャラクターを設定し、「くるみ味噌」という発明(変化)を組み込むことで、訪問者が感情移入できる物語へと昇華しました。
「作って満足」で終わる、出口戦略の不在
パンフレットや動画を作ることがゴールになってしまい、その物語を「どう活用し、観光客の体験価値や消費に繋げるか」という出口戦略が欠けているケースが非常に多く見られます。
文化庁の日本遺産ストーリーサイト
文化庁の「日本遺産」公式サイトは、文化遺産を保存・解説するという目的においては非常に有益ですが、サイト名に「ストーリー」と冠することで、時として「説明文」と「物語」との混同を招きやすい一因とも言えるでしょう。
文学的・物語論的な意味での「物語(ストーリー)」とは、単なる事実の羅列や、情緒的な美辞麗句の連なりではありません。それは、①読者が感情を投影しうる「主人公」、②その主人公が直面する「葛藤」、そして③葛藤の克服を通じて読者に感情的な解放をもたらす「構成」という三位一体の有機的な構築物です。
文化観光におけるストーリー化のゴールとは、まさにこの物語の力を使って人の「行動」を誘発することにあります。
その最も分かりやすい成功事例が「アニメ聖地巡礼」でしょう。優れた物語はファンに強烈な動機を与え、一説には年間250億円とも言われる経済効果を生み出しています。
もちろん、全ての物語がこれほどの力を持つわけではありません。
しかし、物語が持つ本質的な力を理解し、たとえ250億と言われるうちの0.1%でも経済効果を生むような物語を数多く作り出せば、その積み重ねが、やがて地域全体に大きな価値をもたらすのではないでしょうか。

寓話『クラモリさまとウカノケさま』の創作は、プロジェクトのゴールではなく、あくまで始まりに過ぎません。
この物語の真価は、そこからいかにして観光客の「体験」と「消費」へ繋げるか、という明確な出口戦略にあります。
例えば、柳町の企業と連携した「ウカノケさまの知恵くるみ餅」といった土産物開発(フェーズ2)。さらに、長野大学の学生たちと共に、バスツアー客向けの「1時間体験プログラム」(フェーズ3)を造成するなど、物語を起点とした経済活動を設計しています。
「誰に」語るのか? 視点の欠如
「この町の深い歴史を、もっと知ってほしい」。
その熱意が、かえって観光客を置き去りにしてしまうことがあります。
作り手が語りたいことと、お客様が楽しめる時間や知識レベルとの間に、ギャップが生まれてしまうのです。
例えば、上田城下町柳町の主なターゲットの一つである「滞在時間の短いバスツアー客」に、長大な歴史解説は響きません。
そこで私たちは、物語のフレームワークを「秩序 vs 創造」という極めてシンプルな対立構造に設定しました。
これにより、専門知識がなくても誰もが直感的に楽しめる寓話が生まれ、短い時間でも深く印象に残る「体験価値」を提供できるのです。
担当者任せで消える「組織の壁」
「熱意ある担当者が異動したら、企画も立ち消えになった」
「行政の縦割りで、組織的な連携がうまくいかない」
観光事業において、こうした組織の壁は大きな課題です。
そこで本プロジェクトでは、特定の個人や部署に依存しない、「物語創出のエコシステム」そのものを構築することを前提としています。
具体的には、上田城下町観光協会がハブとなり、長野大学とは教育(PBL学習)として、柳町とは地域経済の活性化で連携。これにより、担当者の異動に左右されることなく、学生という未来の力と、地域経済の活力が、継続的に物語を育んでいく体制を目指しています。
価値を翻訳する「物語装置」という考え方
「ことほむ」が提案するのは、地域のあらゆる魅力を再発見するための「物語装置(ナラティブ・エンジン)」そのものです。
この装置の核となるのが、上田の例から理論を分解すると、文化を「秩序(クラモリ)的か、創造(ウカノケ)的か」という、シンプルで強力な二元論のレンズにしたことです。
このレンズを通して町を眺めることで、これまでバラバラに見えていた地域資産が、訪問者自身の頭の中で、次々と意味のある物語として立ち上がってきます。
例えば、歴史ある神社のたたずまいは「クラモリさまの静かな秩序」の象徴となり、一方で、美味だれ焼き鳥のような新しいご当地グルメは「ウカノケさまの自由な創造性」の現れとなる。
ただの路地裏でさえ、「二柱の神様がすれ違った場所かもしれない」と想像力をかき立てる舞台に変わるのです。
食べ物も、お土産も、風景も、すべてがこの装置によって一つの世界観に接続され、訪問者にとって自分だけの特別な物語の一部となります。
「ことほむ」の役割は、この強力な「物語の翻訳機」を設計し、地域に実装すること。
それによって、持続的に価値を生み出し続ける、新しい観光の形を創造します。
あなたの町の「話」にも、きっと価値がある
そのための物語は、どこか遠くから借りてくるものではなく、常に、そこにあります。
それは、その土地に住む人々が、あまりにも当たり前すぎて価値を忘れかけている風景、味、そして日々の営みの中に、静かに眠っているのです。
私たちの仕事は、その眠っている物語の声に耳を澄まし、その土地だけの「当たり前」が持つ本当の意味を、訪問者が理解できる言葉と形で、もう一度この世界に語り直すこと。
そうして語られた物語は、訪問者を単なる傍観者から、その世界の住人へと変えます。
そして、心に生まれた問いと共感は、旅が終わった後もその人の内に残り続け、地域との深く、永い縁となるのです。
そしてナラティブへ。
エンターテイメント的なストーリーもそうですが、そのストーリーが発生するまでのシードとなる「ナラティブ」は近年、AI検索へ移り変わる中では非常に重要になります。
上田柳町は「宇迦之御魂命」と「倉稲魂命」いう2つの神名ナラティブが存在しているので、エンターテイメントとなるストーリーが作れました。