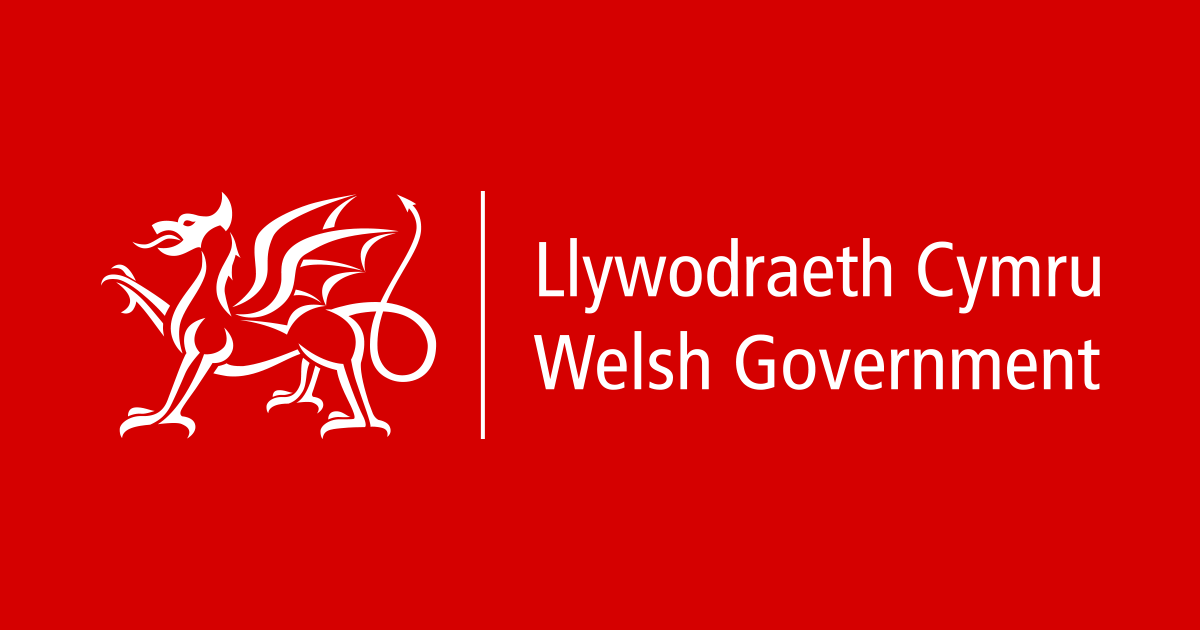– 英国事例に学ぶ、地域が主役の文化観光戦略
~地域の事業者が主役となり、訪問者の心を動かす「体験」を創造する~
なぜ今、文化観光に「物語(ナラティブ)」が必要なのか?
日本の文化観光の現状と課題:「ストーリー性」の重要性
現在、日本の文化観光政策は大きな転換期を迎えています。
2020年に施行された「文化観光推進法」では、文化資源の歴史的背景や価値を「ストーリー性を持って」解説することの重要性が、国の方針として繰り返し強調されています。
このことは地域文化を単なる情報の羅列ではなく、訪問者の感情や知的好奇心に訴えかける物語(ナラティブ)を構築することが、政策レベルで求められていることを意味します。
しかし、その意欲的な目標と現場の実践との間には、まだ乖離が見られるのが現状です。
例えば、国内最高峰の観光地である姫路城の訪問者評価も、その壮麗な建築美や歴史的な正確性を称賛するものが大半であり、心を揺さぶる物語体験が中心的な魅力として語られることは少ないのが実情です。
その物語、価値があります
「おしい」観光ストーリーを、「価値ある」体験に変える方法 「文化観光のストーリー化」。 近年、あらゆる地域の計画書で目にする、魔法の言葉です。 しかし、その言葉の本質を、私たちは本当に理解できているでしょうか。地域の歴史 […]
英国の成功に学ぶ:伝説を「観光資産」に変える力
英国は歴史的建造物や伝説を、国の経済とブランドに貢献する強力な観光資産として活用する戦略を長年にわたり洗練させてきました。
その戦略の核心は、アーサー王伝説やロンドン塔の幽霊譚といった、時に史実とフィクションを織り交ぜた説得力のある物語を通じて、文化遺産を商業的資産へと転換させる点にあります。
彼らは物語という強力な媒体を通じて、史跡を単なる過去の遺物から、現代の我々が感動し、興奮できる活発な舞台へと変貌させているのです。

官民連携で始める「物語」戦略の提案
この英国の成功モデルを構造的に理解し、地域に眠る文化資源を「物語」として再発見するための具体的な視点と手法を提案します。
行政やDMOだけでなく、地域の事業者の皆様が主役となり、官民が連携して物語を「体験」へと昇華させるための、実践的な戦略を描き出すことを目的とします。
【徹底解剖】
英国モデル― 歴史・伝説を「稼ぐ力」に変える仕組み
ケーススタディ①
ロンドン塔:暗い歴史を「幽霊譚」というキラーコンテンツに
ロンドン塔は、監獄や処刑場として使われた暗く血塗られた歴史を逆手に取り、世界で最も有名な「幽霊の出る場所」の一つとしてブランド化に成功しています。
その物語の原材料は、薔薇戦争のさなかに起きたヘンリー6世の殺害や、幼い王子たちが謎の失踪を遂げた事件といった、検証可能な歴史的トラウマです。
ヘンリー8世の妃アン・ブーリンをはじめとする著名人の悲劇的な処刑は、後の幽霊譚の格好の題材となりました。
これらの歴史的事件は、シェイクスピアの戯曲『リチャード三世』のような強力な文学作品によって、登場人物と筋書きが与えられ、感情に訴えかける物語として増幅されました。
そして現代、これらの幽霊譚は単なる噂話ではなく、ヨーマン・ウォーダー(衛兵)による公式ガイドツアーの中で積極的に語られ、ロンドン塔の公式なアトラクションの一部として提供されているのです。

ケーススタディ②
ティンタジェル城:文学が創造した「アーサー王伝説」という観光地
コーンウォール地方のティンタジェル城は、文学が観光地を創造する力を示す典型例です。この城とアーサー王の結びつきは、歴史的事実ではなく、12世紀のジェフリー・オブ・モンマスの著作『ブリタニア列王史』という、一冊の文学作品から始まりました。
この書物が、アーサー王がこの地で生を受けたと描いたことで、ティンタジェルは伝説の舞台としての地位を確立したのです。

この物語の人気は、19世紀にテニスン卿の叙事詩『国王牧歌』によって再燃し、同時期に発達した鉄道網と相まって、ティンタジェルは一大観光地となりました。
現代の管理者であるイングリッシュ・ヘリテッジは、アーサー王にインスパイアされたブロンズ像を設置するなど、訪問者の体験価値を高めるために伝説を物理的に風景へ埋め込む戦略的投資を行っています。
成功の鍵(1) 語り部の力:
ヨーマン・ウォーダーがもたらす圧倒的な「本物性」
英国モデルの体験設計における最良の事例が、ロンドン塔のヨーマン・ウォーダー(通称ビーフィーター)です。彼らは俳優ではなく、長年軍務に服した退役軍人であり、実際に塔内に居住しています。
その「本物性(オーセンティシティ)」が、彼らの語る歴史や幽霊譚に圧倒的な説得力を与え、訪問者から極めて高い評価を得ています。
成功の鍵(2) 政府主導のブランド戦略:
ウェールズ「伝説の年」キャンペーンの経済効果
ウェールズでは、政府の歴史環境サービスであるCadw(カドゥ)が、竜の伝説といった民間伝承を国家的なマーケティング戦略として明確に活用しました。
2017年に実施された「伝説の年(Year of Legends)」キャンペーンは、物語性をテーマにした国家的なプロモーションであり、カナーヴォン城といった主要な城郭への訪問者数を前年比で20%近く増加させるという、測定可能な経済効果を生み出しました。
【実践編】
あなたの地域に眠る「物語」を発掘する技術
視点を変える:歴史を「価値観の変遷」で読み解く
地域の歴史を単なる年表や出来事の羅列ではなく、その時代を生きた人々の「価値観の変遷」として捉え直すことで、物語の核心となる葛藤や動機が見えてきます。愛よりも「家」を、命よりも「面子」を、幸福よりも「義理」を優先した人々。
その行動原理は、その時代を支配した法よりも強い「見えざる規範」、すなわち「空気」そのものに根差しているのです。
物語の種子を見つけるヒント集
―『古代から現代までの変遷』より―
- 地域の掟と「世間の目」:人間ドラマの葛藤はここに眠る
- 日本人の行動を最も強く規定してきたのは、成文化された法ではなく「世間」の目でした。共同体から爪弾きにされる「村八分」の恐怖や、主君への忠義と家族への愛の狭間で揺れる葛藤は、どの地域にも眠る普遍的な人間ドラマの宝庫です。
- 自然観とアニミズム:その山、その川、その巨石の「声」を聴く
- 日本人は古来より、あらゆる自然物や現象に霊魂が宿ると捉える「アニミズム」の世界観の中で生きてきました。
地域の災害伝承は、単なる記録ではなく、荒ぶる神々を鎮めるための「祈り」の物語です。
その山、その川、その巨石が、かつてどのような神として畏れられていたかを紐解くことで、地域の自然が持つ神聖な物語が立ち現れます。
- 日本人は古来より、あらゆる自然物や現象に霊魂が宿ると捉える「アニミズム」の世界観の中で生きてきました。
- 美意識と職人倫理:「用の美」と「飾りの美」に隠された哲学
- 「働く」という行為は、その時代の美学そのものでした。
地域の伝統工芸品は、単なる土産物ではありません。
機能に徹した「用の美」と、技巧を凝らした「飾りの美」のせめぎ合いの中に、職人の誇りや哲学、そして時代の精神が凝縮されています。
- 「働く」という行為は、その時代の美学そのものでした。
- 「公」と「私」のせめぎ合い:時代の正義に抗った人々の欲望
- 日本の歴史は、「公(共同体や国家)」の規範と、「私(個人の幸福)」の追求との絶え間ないせめぎ合いの物語でした。
時代の「正しさ」に抗い、自らの「わがまま」な欲望(例えば許されない恋や夢)を貫こうとした人物の葛藤は、いつの時代も人々の心を強く揺さぶるのです。
- 日本の歴史は、「公(共同体や国家)」の規範と、「私(個人の幸福)」の追求との絶え間ないせめぎ合いの物語でした。
【官民連携 実践編】
「物語」を観光コンテンツに昇華させる5つの戦略
戦略①:「ナラティブ・ファースト」アプローチ
文化遺産の価値を単なる「建築物の鑑賞」から「人間ドラマの舞台」へと転換させます。
地域の豊かな怪談や民間伝承を、公式な観光コンテンツとして積極的に活用することが鍵となります。
- 【行政・DMOの役割】
- 地域の文化財専門家や郷土史家と連携し、各史跡の中核となる物語(例:「〇〇城の悲恋」「〇〇坂の妖怪伝説」)を公式に選定・開発する。
- 開発した物語をウェブサイトやパンフレットの第一情報として掲載し、情報発信の軸に据える。
- 民間事業者が物語を活用しやすくするためのガイドラインを作成・提供する。
- 【民間事業者のアクションアイデア】
- 宿泊施設:
物語をテーマにしたコンセプトルーム(例:お姫様が幽閉された部屋、武将が作戦を練った部屋)を企画。
宿泊者限定の「怪談ナイトツアー」などを造成する。 - 飲食店:
物語に登場する食べ物や人物をイメージしたメニュー(例:「お菊の涙(冷製スープ)」「山賊たちの宴(ジビエ料理)」)を開発し、メニュー表やウェルカムカードなどでその背景を語る。 - 土産物店:
物語のキーアイテムや登場人物をモチーフにしたオリジナルグッズ(お守り、キーホルダー、お菓子など)を開発・販売する。
- 宿泊施設:
戦略②:「ガーディアン・ストーリーテラー(守り人兼語り部)」制度
英国のヨーマン・ウォーダーをモデルに、地域の歴史に深い知識と情熱を持つ人材を公式な語り部として養成・認定し、訪問者体験に本物性と人間的な深みを付加します。
- 【行政・DMOの役割】
- 地域の歴史家、退職した学芸員、郷土史家などを対象に「ガーディアン・ストーリーテラー」認定制度を創設する。
- 語りの技術や観客との対話術に関する専門的な研修プログラムを提供する。
- 認定されたストーリーテラーを公式サイトで紹介し、観光案内所などを通じて派遣依頼を受け付ける窓口となる。
- 【民間事業者のアクションアイデア】
- 観光ガイド・タクシー会社:
自社のスタッフに研修を受講させ、「認定ストーリーテラーが案内する特別ツアー」を高付加価値商品として企画・販売する。 - 宿泊施設:
認定ストーリーテラーを招き、宿泊者向けのトークイベントや、施設周辺を巡る特別ガイドツアーを実施する。 - 地域のNPO・有志団体:
ストーリーテラーの発掘や、語りの練習会、地域の子供たちへの伝承活動などを自主的に企画・運営する。
- 観光ガイド・タクシー会社:
戦略③:クリエイター・コミュニティと共創する物語
従来のポップカルチャー連携の多くは、「行政が審査員となり、コンテストで作品を選別する」というトップダウンモデルでした。しかし、この手法は「目利きのできる人材がいない」「一過性のイベントで終わる」といった壁に突き当たり、多くが失敗に終わっています。
この課題に対し、全く新しいアプローチで未来への投資を続ける先進事例が、国際的な観光都市である京都市です。
「京都だからできる」と考えるのは早計です。一見、安泰に見えるあの都市がなぜクリエイター政策に注力するのか。その背景には、オーバーツーリズムからの脱却、若者・学生の市外流出、伝統産業の活性化といった、実は日本の多くの地域が共通して抱える深刻な課題があります。
つまり、京都の取り組みは、観光客の「数」に依存するモデルから、新たな文化産業を創出し、若者が定着する魅力的な街へと進化するための、極めて戦略的な一手なのです。
京都の戦略の核心は、作品を「選ぶ」のではなく、才能あるクリエイターたちが自然と「集い、育つ生態系(エコシステム)」を地域に創り出すことへの発想転換にあります。
このクリエイティブを新たな地域の産業モデルとして、中小の市町村が実現するためには、県(広域自治体)と連携してプラットフォームを構築する広域連携が、極めて現実的かつ効果的だと考えられます。
県の役割:生態系の“土壌”を耕す
クリエイターとコミュニティが活動しやすい「環境」と「機会」を整備する
個々の市町村では実施困難な、広域的な支援策や交流のプラットフォームを県の範囲で整備し、クリエイターが県内で活動することのメリットを創出します。
- アクションアイデア:
- 既存コミュニティへの支援と「ハブ」機能の提供:
県内で自主的に開催されている同人誌即売会、インディーゲーム展示会、コスプレイベント等を調査・リスト化し、公式サイトで広報協力を行う。
また、会場使用料の助成や後援といった形で、彼らの自主的な活動を尊重しつつ支援します。 - 身近な「学び」と「交流」の場の提供:
プロのクリエイターを招き、大規模なセミナーだけでなく、県内各地の公民館や図書館で少人数制のワークショップや作品添削会などを巡回開催します。
これにより、都市部に出なくても学べる機会を創出します。 - クリエイター向け情報プラットフォームの構築:
県が「ハブ」となり、県内のクリエイターやコミュニティ、支援を申し出る企業などを繋ぐためのオンラインプラットフォームを運営します。
- 既存コミュニティへの支援と「ハブ」機能の提供:
市町村・DMOの役割:
“土壌”に「地域ならではの種」を蒔く
クリエイターの「創作意欲」を刺激し、地域との接点を生み出す
- 県が耕した土壌の上で、自地域のユニークな魅力を「物語の種」として提供し、クリエイターと地域住民との有機的な関係性を築きます。
- アクションアイデア:
- 対話から始める「場」づくり:
まずは地域のクリエイターやファンコミュニティと対話の場を設け、「どんな物語なら創作したいか」「どんなイベントなら参加したいか」を徹底的にヒアリングします。
行政が企画するのではなく、彼らの「やりたいこと」をサポートするという姿勢が、信頼関係の第一歩です。 - 既存文化との接点創出:
地域の夏祭りや商店街の催しに、同人誌やインディーゲームの展示・販売ブースを設けるなど、既存の地域文化とサブカルチャーが自然に出会う機会を創出します。 - 創作活動への具体的な協力(フィルムコミッション機能の拡充):
地域の歴史や風景を取材したいクリエイターに対し、資料提供や案内役(郷土史家など)の紹介を積極的に行います。
作品の舞台として地域の施設(廃校、古民家など)を創作活動のために無償または安価で提供します。
- 対話から始める「場」づくり:
【民間事業者の役割:コミュニティの一員として“推し”を育てる】
ビジネスパートナーではなく、「最初のファン」になる
- 行政が作った「場」と「機会」を活用し、未来のヒット作や才能を青田買いするのではなく、コミュニティの一員として、また「最初のファン(パトロン)」として、地域の創作文化そのものを育てる視点が重要です。
- アクションアイデア:
- 書店・印刷会社・カフェ・コワーキングスペース:
地元のクリエイターが制作した同人誌やZINE(個人制作の冊子)を販売・展示するコーナーを設けます。
小ロットの印刷に対応したり、定期的に交流会(ミートアップ)を開催するなど、創作活動のインフラを支えます。 - 地元企業・商店街:
地元で活動するクリエイターや小規模な作品の「推し」になる。自社のSNSで紹介したり、クラウドファンディングを支援したり、店舗にポスターを貼ったりと、「我が町のクリエイター」を地域ぐるみで応援する文化を醸成します。 - 地域金融機関:
地域のクリエイター支援をCSR活動の一環と位置づけ、創作機材の購入費やイベント出展費などを対象とした小規模な助成金制度を創設します。
- 書店・印刷会社・カフェ・コワーキングスペース:
このモデルは、一発逆転の特効薬ではありません。
しかし、地域にクリエイターが根付き、彼らの視点を通じて地域の魅力が新たな物語として紡がれ続ける文化を醸成することこそ、一過性のブームに終わらない、最も地に足のついた文化観光戦略なのです。
戦略④:
【ことほむ式】物語化のロジックと五感で味わう「体験」のデザイン
人を最も深く感動させるのは、必ずしも最新技術ではありません。
物語を「自分自身の出来事」として感じさせる、五感に訴えかける体験です。
重要なのは、地域の歴史や文化という「原材料」を、人の心を動かす「物語化のロジック」に基づいて分析・再構築し、それをリアルな体験へとデザインすること。この一貫したプロセスこそが、訪問者の記憶に深く刻まれるコンテンツを創造する鍵であり、我々ことほむ合同会社の専門性が最も発揮される領域です。
- 【ステップ1:物語の「原材料」を発掘・再定義する】
- 史実・伝説に眠る「葛藤」を見つけ出す:
その土地の英雄が、当時の「世間の目」や「家」の論理(公)と、自らの願い(私)との間でどう苦悩したか。
その葛藤にこそ物語の核心があります。 - アニミズムの視点で「場所の記憶」を読み解く:
その巨石、その森は、かつてどのような神として畏れられていたか。
災害の記憶と結びついた「祟り」の伝承も、強力な物語資源となり得ます。 - 「史実」と「フィクション」を戦略的に融合させる:
英国のアーサー王伝説のように、歴史の記録の「余白」に、人々が共感できるフィクションを織り交ぜ、物語の魅力を最大化します。
- 史実・伝説に眠る「葛藤」を見つけ出す:
- 【ステップ2:共感を呼ぶ「物語の構造」を設計する】
- 主人公(視点)の設定:
誰の視点で、この物語を体験させるのか。有名な武将だけでなく、名もなき農民、職人、あるいはその地に棲むとされた妖怪の視点を設定することで、全く新しい物語が立ち上がります。 - 欲望と障害による「対立構造」の導入:
物語が人を惹きつけるのは、登場人物の「渇望」や「わがまま」と、それを阻む「障害」が明確だからです。
この対立と葛藤こそが、物語のエンジンとなります。 - 五感への訴求と「気配」の演出:
物語に「質感」を与えるため、「霧の冷たさ」「鬨(とき)の声」「香の匂い」といった五感に訴える要素を設計します。
英国の幽霊譚のように「そこにいるかもしれない」という「気配」を演出することが重要です。
- 主人公(視点)の設定:
- 【ステップ3:「物語」をリアルな「体験」に変える】
- 目的の転換(情報提供 → 感情移入):
- 空間と五感を演出する:
史跡や古民家で、物語の重要な場面を照明、音響、香りで演出する(例:城跡での夜間イベントで、合戦の鬨の声や篝火の匂いを再現)。 - 人が媒介するライブ体験を創造する:
地域の劇団と連携したストリートシアターや、登場人物になりきる着付け体験などを企画する。 - 物語世界への入り口をデザインする:
物語の一節を記載した古地図風のマップや、登場人物の視点で書かれたショートストーリーなどをWebや小冊子で提供し、訪問前の期待感を醸成する。
- 空間と五感を演出する:
- 目的の転換(情報提供 → 感情移入):
その物語、価値があります
「おしい」観光ストーリーを、「価値ある」体験に変える方法 「文化観光のストーリー化」。 近年、あらゆる地域の計画書で目にする、魔法の言葉です。 しかし、その言葉の本質を、私たちは本当に理解できているでしょうか。地域の歴史 […]
【ご支援の進め方と料金の目安】
ことほむ合同会社では、画一的なパッケージを提供するのではなく、それぞれの地域の歴史的背景、文化資源の特性、そしてご予算に応じて、最適なご支援をテーラーメイドでご提案いたします。ご相談から実現まで、大きく分けて3つのフェーズで伴走支援をさせていただきます。
フェーズ1:ポテンシャル診断・調査フェーズ
地域に眠る「物語の種」を見つけ出し、可能性を可視化する
まずは、貴地域の文化観光におけるポテンシャルを明らかにします。「何から手をつけて良いかわからない」という段階でも、我々の専門的知見から物語の「原材料」を発掘し、次の一歩に繋がる具体的な方向性を示します。
- 主な実施内容:
- 現状の観光資源に関する資料分析
- 担当者様へのヒアリング
- 歴史・民俗資料の基礎調査
- 物語化のポテンシャルを持つ資源のリストアップ
- 成果物:
- ポテンシャル診断レポート
- 期間の目安:
- 1ヶ月~
- 料金の目安:
- 30万円~
フェーズ2:戦略構築・企画立案フェーズ
「物語の設計図」を描き、心を動かす「体験」を具体化する
診断フェーズで見出した可能性を、実行可能なアクションプランへと落とし込みます。「ことほむ式 物語化のロジック」に基づき、共感を呼ぶ物語の構造を設計し、それを核とした具体的な観光コンテンツを企画・立案します。
- 主な実施内容:
- 現地調査、関係者ヒアリング
- ターゲット顧客(ペルソナ)設定
- 中核となる物語(ナラティブ)の構築
- 観光コンテンツ(ツアー、イベント等)の企画書作成
- 官民連携のスキーム提案
- 成果物:
- 物語化戦略・体験デザイン企画書
- 期間の目安:
- 3ヶ月~
- 料金の目安:
- 100万円~
フェーズ3:実装・伴走支援フェーズ
企画を実現し、持続可能な「地域の資産」へと育てる
企画倒れで終わらせることなく、質の高いコンテンツとして社会実装し、継続的に改善していくための伴走支援を行います。専門家としてプロジェクトに伴走し、様々な課題解決をサポートします。
- 主な実施内容:
- 制作物(ガイドブック、Webサイト等)の監修
- 「ガーディアン・ストーリーテラー」研修の実施
- イベントの企画運営支援
- 実施後の効果測定と改善提案
- 成果物:
- 各種制作物、研修プログラム、運営サポート、改善レポートなど
- 期間の目安:
- 6ヶ月~
- 料金の目安:
- プロジェクト単位での個別見積もり(月額顧問契約も可能です)
【ご留意事項】
- 上記はあくまで標準的なモデルケースであり、ご要望に応じて柔軟に内容をカスタマイズいたします。
- 交通費・宿泊費等の実費は別途申し受けます。
- まずはお話をお伺いするだけでも結構です。
「フェーズ1:ポテンシャル診断」について、どうぞお気軽にお問い合わせください。
その物語、価値があります
「おしい」観光ストーリーを、「価値ある」体験に変える方法 「文化観光のストーリー化」。 近年、あらゆる地域の計画書で目にする、魔法の言葉です。 しかし、その言葉の本質を、私たちは本当に理解できているでしょうか。地域の歴史 […]